誕生ストーリー
野菜とともに育った、agreensの物語
戦後の混乱の中で、
農業と商いに向き合った原点。
1958年、南あわじ市(旧南淡町)。
仕事も少なく、先行きの見えにくい時代のなか、農業と地域の暮らしを支えたいという想いから、高川悦郎は動き始めました。
自ら畑に立ちながら、産地業者のもとで商いの知恵を学び、地元の農家から仕入れた野菜を、市場へと届ける日々。
そうした積み重ねの中で、少しずつ信頼を築き、地域の農産物流通の一端を担う存在へと育っていきました。
同じように農家と市場を結ぶ人は当時も多くいましたが、高川商店は、「農業に近い目線で商いを続けたこと」、そして「生産者との関係性を何よりも大切にしたこと」で、やがて南あわじに根づく存在へと成長していきました。
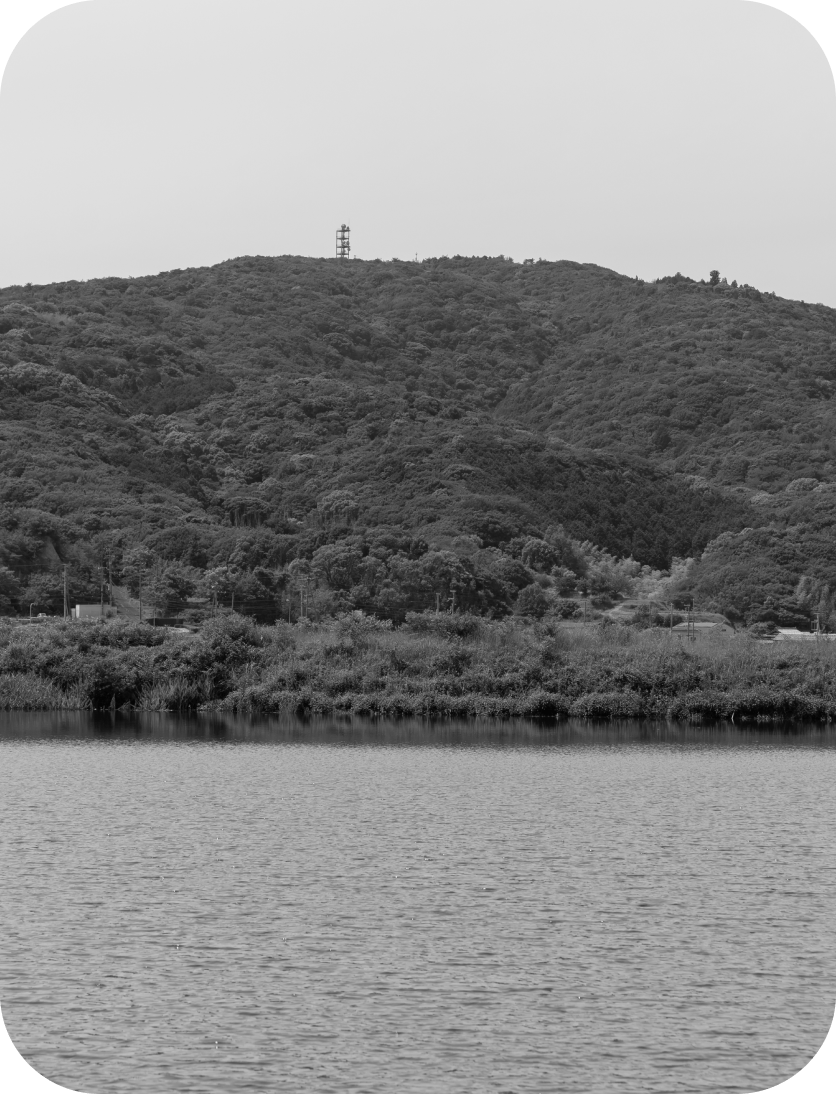
淡路玉ねぎが「全国の味」に
なったわけ。
淡路島の玉ねぎが特別なのには、理由があります。
温暖な気候、やわらかな潮風、排水性の高い土壌——
この島には、玉ねぎをおいしく育てる条件が揃っていました。さらに、「秋まき・春収穫」という長期育成の方法をとることで、玉ねぎはゆっくりと糖度を蓄え、やわらかく、辛みの少ない風味に育ちます。やがて「淡路の玉ねぎはうまい」との評判が市場に広がり、地域一体となったPRや流通の工夫により、“淡路玉ねぎ”は全国区のブランドへと進化していきました。agreensのルーツは、まさにこの淡路の大地にあります。
玉ねぎがブランドになる、その背景には、長年にわたって土と向き合い続けてきた人々の想いがあるのです。


“つくる”だけでは、農業は守れない。
1980年代、高川元太郎が2代目として代表に就任。日本経済はバブルの絶頂期を迎え、都市部では外食産業が急速に拡大。それに伴い、調理現場の効率化を支える「カット野菜」という新たな市場が動き始めた時代でもありました。
「この流れは、いずれ加速していく。農業だけにとどまらず、加工や流通までを視野に入れた“仕組み”をつくるべきだ」——そんな想いのもと、1989年に淡路マルマサフード株式会社を設立。
地元の野菜に新たな価値を加え、より多くの人へ届けるために、加工・販売までを自社で手がける体制づくりに着手。1999年には現在の本社工場を新設・移転しました。
つくるだけで終わらせない、農業の未来を見据えた挑戦が、本格的に始まりました。

自社栽培の開始。
変わりゆく時代への対応。
2022年、agreensは自社栽培を本格的に開始。
その背景には、農業を取り巻く環境の急速な変化がありました。
高齢化、後継者不足、価格の不安定化といった構造的な課題に加え、コロナ禍や「2024年問題」など、物流や人材に関する新たな制約も浮上してきました。
従来のように全国から安く大量に仕入れて流通させる仕組みは限界を迎えつつあります。だからこそagreensは、地産地消を意識した、工場から近い場所での栽培に力を入れ始めました。
加えて、環境問題への企業責任がより強く問われる時代。グローバルからローカルへ、ただの効率ではなく、「持続可能な仕組みづくり」を見据えた動きへと舵を切りました。

農業を、もっと多様で、
持続可能なものへ。
令和の時代。3代目・高川泰輔は、今の農業が直面する「続けたくても続けられない」現実に向き合います。
「農業に関わりたい人はいる。でも、全員が“育てる”のが得意とは限らない。」だからこそ、育てる人・加工する人・運ぶ人・支える人——それぞれの力が集まって、農業は未来へとつながると考えました。
2025年、私たちは「agreens株式会社」へと社名を変更。
“agriculture(農業)”דgreen(持続可能)”ד淡路島のa”
その名に、これまでとこれからのすべての想いを込めました。agreensは、育て・活かし・届ける農業の仕組みを自社で完結させることで、フードロスを減らし、地域雇用を生み、そして日本の食卓と農業をつなぎ直しています。


私たちが育てているのは、野菜だけじゃない。
agreensが本当に育てたいのは、“農業には未来がある”と、誰もが信じられる社会です。
甘くて、やわらかくて、やさしい。けれど本当は、たくましくて、誇り高い。そんな淡路玉ねぎのような農業を、次の世代へ。
agreensは、これからも土地と人と想いを結び、“続く農業”の物語を、育てていきます。
お問い合わせ
お問い合わせは、以下のフォームより
お願いいたします。
-

お電話でのお問い合わせ
 0799-55-1777
0799-55-1777受付時間/平日9:00〜17:00(土日祝休み)
-

WEBでのお問い合わせ
